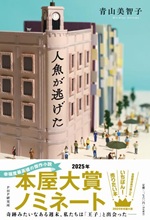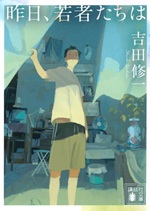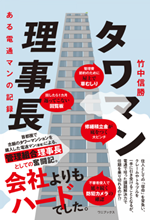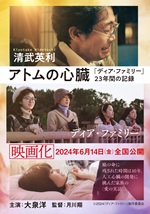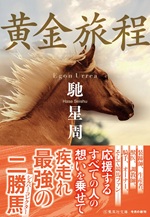私の本棚
清水ひろしが最近読んだ本をご紹介いたします。
『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか? 認知科学が教えるコミュニケーションの本質と解決策』今井むつみ 著

- 出版社:日経BP
「人間はわかり合えないもの」であり、相手に「言えば伝わる」「話せばわかる」と私たちが考えていることは幻想に過ぎない。それは、①相手の言葉を理解する際のバックグラウンドにある「スキーマ」(認知、知識や思考の枠組み)がそれぞれ異なり、かつ、②認知能力はあやふやだからである、と著者は述べています。そして、このことを双方が理解しておくことが理想だと記しています。
そもそも、脳はすべてを正しく覚えておくことはできず、忘れるものであり、偏りも生じ、感情によって記憶もねじ曲がってもいきます。また、人間は意思決定の際、最初に感情で物事を判断し、その後、「論理的な理由」を後づけしているに過ぎず、意思決定を「直観」で行っています。
このように、人間は皆「信念バイアス」「認知バイアス」といった何らかのバイアスを持っていることを意識することが必要です。
*信念バイアス:「自分が「こうしよう」というものを、「他人にもそうさせよう」というもの
*認知バイアス:自分の考えや経験、自分の周囲の人の考えや経験という非常に狭いサークルである「自分の小さな世界」を「基準」として世界を見てしまう。
そのうえで、筆者は以下のように訴えています。
私たちは、AIには代替できない、人間にしかない能力を磨くことが求められており、それこそが、生きた知識、直観であり、学びとはこうした能力を磨いていくことだ、ということを忘れてはいけない。
『昨日、若者たちは』 吉田 修一 著
『タワマン理事長 ある電通マンの記録』 竹中信勝 著
『アトムの心臓 「ディア・ファミリー」23年間の記録』清武英利 著
『サラブレッドはどこへ行くのか 「引退馬」から見える日本競馬』 平林健一 著
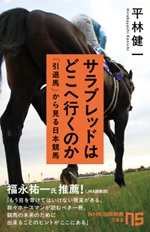
- 出版社:NHK出版新書
サラブレッドの一生に関わるさ様々な人たちへの取材をもとにまとめられた一冊。平林氏は、引退馬の問題を扱ったドキュメンタリー映画「今日もどこかで馬は生まれる」を制作している。映画を企画した2017年から7年が経過するなか、「ウマ娘」の影響などもあり引退馬支援への動きを著者は感じている。
引退馬問題に最も責任のあるのはJRAだとし、「競馬を楽しみながら引退馬支援を行える」取組みを求めています。また、メディアには、ポジティブな情報だけでなく引退馬に関する頭数やコストなど、実情の一端を正しく発信してほしい、と述べています。
そのうえで、引退馬の現状に違和感を持つ全ての人に、どんな些細なことでもいいから自分ができることをやってみてほしい、と訴えています。
『黄金旅程』馳星周 著
『「指示通り」ができない人たち』 榎本博明 著
『母という呪縛 娘という牢獄』 齊藤 彩 著
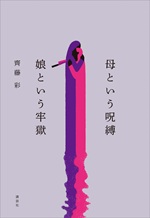
- 出版社:講談社
2018年に起きた、滋賀県在住の看護学生(逮捕時は看護師)が母親を殺害し、死体損傷、遺棄した事件のノンフィクション。
子どものころから母親による体罰等を受け、9浪させられ大学看護学科に進学していた。
母と娘のLINEのやり取りや、著者が被告との面会や手紙のやり取りを通じてまとめられている。体罰や言葉の暴力を浴びせる母親、その母親から逃げようと家出を繰り返す娘、一方で娘と旅行をしたり、一緒にお風呂に入るような母親。
娘は裁判で「私か母のどちらかが死ななければ終わらなかったと、現在でも確信している」と述べている。
いびつな親子をまわりが察知し対応していたならば、こんな悲劇は起こらなかったのではないか、もっと早い段階で健全な生活を取り戻すことが出来たのではないか、・・・そんなことなどを思った一冊です。
『ぼくのニセモノをつくるには』 ヨシタケシンスケ 著
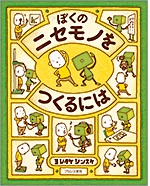
- 出版社:ブロンズ新社
宿題やお手伝いなどをやりたくない けんたくんは、自分の「ニセモノお手伝いロボット」を買って、全部やってもらうことを思いつきます。完璧なニセモノを目指すロボから、人となりをあれこれ質問攻めさるけんたくんは、「自分とは?」と自問していきます。
著者が読者に伝えたかったのは、けんたくんが言っている以下のことだと思います。
ぼくはひとりしかいない。
おばあちゃんが いってたけど にんげんは ひとりひとり かたちがちがう 木のようなものらしい。
じぶんの木の 「しゅるい」は うまれつきだから えらべないけれど それを どうやって そだてて かざりつけするかは じぶんで きめられるんだって。
木の おおきさとかは どうでもよくて じぶんの木を 気にいってるかどうかが いちばん だいじらしい。