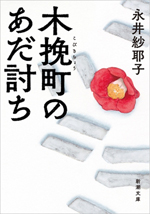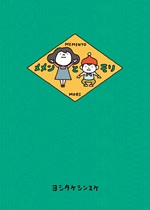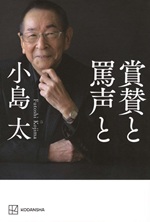私の本棚
清水ひろしが最近読んだ本をご紹介いたします。
『木挽町のあだ討ち』 永井 紗耶子 著
『静かな退職という働き方』 海老原嗣生 著
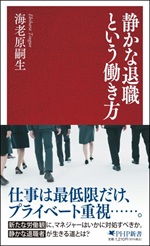
- 出版社:PHP新書
静かな退職という働き方 海老原嗣生 PHP新書
「静かな退職」とは、会社を辞めるつもりはないものの、出世を目指してがむしゃらに働きはせず、最低限やるべき業務をやっているだけの状態のこと。
著者は、日本の働き方や給与システムについて以下のように述べています。
日本人が今までやって来た働き方は、ブルシット・ジョブ(あってもなくても変わらない意味のない仕事の蔑称)の塊であり、「やっている感」を示すだけの行為でしかない。
また、「全員階段を上る」キャリアしかなく、多くの日本人が当たり前と思っている「役職が同じままでも、給料は年齢とともに上がる」という常識は世界の非常識であり、この部分を変えないと、日本の雇用問題は解決できない。
そんななか、近年は女性の社会進出によって会社の縛りは弱まり、プライベートを重視して仕事を抑える「静かな退職者」が増えてきた。「静かな退職者」が市民権を獲得し始め、今後、ブームになっていくと考えられる。
しかし、これまでの考え方である管理職や上司には理解が進まず、「静かな退職者」と軋轢が生じている。経営側には、「静かな退職者」こそ、企業の経営環境を劇的に好転させ、人材管理を進化させる魔法の杖だ、と気づいてほしい。
さらに、政府は今でも政策の軸足を「忙しい毎日」に置いている。まずここにボタンの掛け違いがある。もっと努力し頑張ろう、という「人への投資」という名で進められている政策、リスキリングなどはその典型である。
焦点を当てるべきは、「欧米では、なぜ、低レベルのサービスでも高賃金が稼げるのか?」であり、「そんなに頑張らなくても、いいんだよ」「いやむしろ、頑張らない方が生産性は上がるんだ」と、日本もその方向に政策誘導し、「忙しい毎日」から脱し、「静かな退職」を政策の軸にしてほしい。
これからは「緩く長く」「錆びずに」働ける仕組みが重要になってくる。
『メメンとモリ』 ヨシタケシンスケ 著
『今日未明』 辻堂ゆめ 著
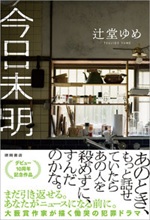
- 出版社:徳間書店
ネットに流れる数行の短いニュースに、「またこんな事件が」と思うことはないだろうか。
■自宅で血を流した男性死亡 別居の息子を逮捕
■マンション女児転落死 母親の交際相手を緊急逮捕
■乳児遺体を公園の花壇に遺棄 23歳の母親を逮捕
■男子中学生がはねられ死亡 運転の75歳女性を逮捕
■高齢夫婦が熱中症で死亡か エアコンつけず
これらの報道を、われわれは先入観や固定観念をもって勝手に判断していることがある。そして、SNSに詳細も分からずに見解を発信していく人たちもいる。本書に掲載された5つの短編は、その事象の背景にある真実や当事者たちの思いを、読者の最初の予想を裏切るかたちで描いている。各短編だけでなく、エピローグまでとても練られている作品だと感じました。
『賞賛と罵声と』 小島 太 著
『日本史 敗者の条件』 呉座勇一 著
『でっちあげ 福岡「殺人教師」事件の真相』 福田ますみ 著
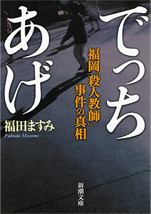
- 出版社:新潮文庫
ドキュメンタリー作品。「殺人教師」としてマスコミにも叩かれ、停職6か月の処分を受けた小学校教師。しかし、民事裁判を通して、全く事実に反する真相が明らかになる。
著者は次のように述べています。
子供は善、教師は悪という単純な二元論的に凝り固まった人権派弁護士、保護者の無理難題を拒否できない学校現場や教育委員会、軽い体罰でもすぐに騒いで教師を悪者にするマスコミ、弁護士の話を鵜吞みにして、かわいそうな被害者を救うヒロイズムに酔った精神科医。そして、クレーマーと化した保護者。結局、彼らが寄ってたかってこの教師を「史上最悪の殺人教師」にでっちあげたというのが真相だろう。バイアスのかかった一方的な情報が人々を思考停止に陥らせ、集団ヒステリーを煽った挙句、無辜の人間を血祭りに上げたのである。
その後、冤罪として教育委員会による教師の処分はすべて取り消された。
この事件から20年以上が経過をしたが、冤罪や、真偽不明な情報に騒ぐような状況は、個人がSNSで発信する時代になり、むしろその怖さは広がったと言えるのではないでしょうか。
福田ますみ『でっちあげ 福岡「殺人教師」事件の真相』(新潮文庫刊)
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』 三宅香帆 著

- 出版社:集英社新書
「そもそも本が読めない働き方が普通とされている社会って、おかしくない!?」
就職をしたことによって、好きな読書が出来なくなった生活に著者自身が疑問をもち、どうすれば「労働」と「文化」を両立出来るのか、日本の働き方について示しています。
読書とは、自分から遠く離れた文脈に触れること、と定義し、映画「花束みたいな恋をした」の主人公二人の生活を引用しながら、本を読むことは働くことのノイズになる、読書のノイズ性こそが90年代以降の労働と読書の関係であったと指摘しています。
しかし著者は、私たちはノイズ性を完全に除去した情報だけを生きるのは無理だ、と述べています。
だからこそ、働いていても本を読む余裕のある「半身で働く」ことが当たり前の社会をつくろうと提言しています。
日本に溢れている、「全身全霊」を信仰し、「無理して頑張った」を美談とする社会をやめ、仕事に限らず「半身こそ理想」だ、とみんなで声をあげよう、と訴えています。
読後、映画「花束みたいな恋をした」を鑑賞しました。