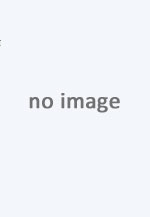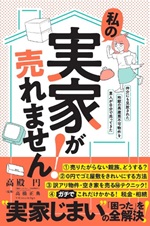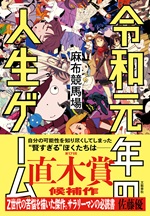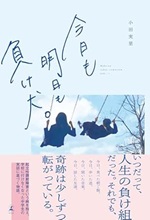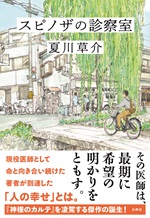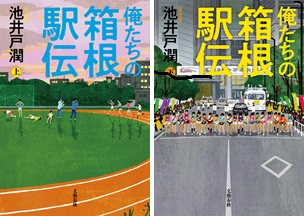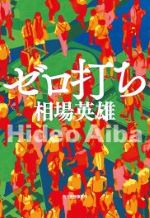2024年9月24日
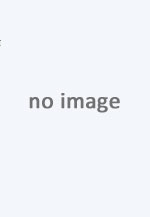
〇発達障害は、生まれつき脳の一部の機能に障害があることが原因で発症するものであり「子どものときから抱えている障害」と言える。親の育て方や養育環境、仕事や生活上のストレスが原因で発達障害を発症することはない。いわゆる「心の病」とは全く異なる。
〇2007年から特別支援教育が導入され、2012年文科省調査によると、知的発達に遅れはないものの学習面や行動面で著しい困難を示す子ども、すなわち発達障害の傾向が疑われる子どもは6.5%、2022年の調査では8.8%であり、小中学生の80万人に相当する。
〇受診者の半数以上が実際には障害ではない。その背景には、①発達障害の人が増えたというよりも、親や教師の理解が進んだことによって疑いをもつ人が増えたこと ②一方で、社会になじめない人、人とうまくコミュニケーションがとれない人が相当数おり、日々悩んでいるという実態がある。
また、子どもの診察にきた母親が、発達障害の傾向をもっていることに気づくことがあり、母親も生きづらさを感じてきたことが推察される。
〇発達障害の子どもの適切な養育環境、大切なことは二つにつきる。
1 特性を認め、受け入れて、その特性を変えようとしないこと
2 得意なこと、好きなことを見つけ出し、それに没頭できる機会を与え、その能力を伸ばしてあげられるようなサポートをすること
つまり、発達障害の本人を変えるのではなく周りがあわせること、である。社会不適応がなくなれば、発達障害の人が社会参加しやすくなる。
〇昭和医大烏山病院などで取り組んでいる発達障害専門のデイケア・ショートケアプログラムでは、同じ障害や疾患をもつ人同士が対等な関係でコミュニケーションをとり、情報交換をしたり、相談し合ったりすることで、お互いを支え合う援助法「ピアサポート」を行っている。ASDの人にはピアサポートが非常に効果的であり、彼らにとって安心できる「居場所」となっている。
〇高い能力やスキルを発揮できるにもかかわらず、障害者枠で雇用されている場合は非常に低い給与になっている。都合よく利用されてしまってはならず、ASDの人が障害者ではなく納税者として社会で生きることができるようになることを願っている。
〇ASDの代表されるような、でこぼこの激しい人も社会で受け入れ、支援しながら活躍してもらおうという、ダイバーシティ&インクルージョン(多様な人材を受け入れ尊重し、相互に機能している状態)の考え方が広まりつつある。
でこぼこをならそうとするのではなく、得意なこと、本人が好きなことを伸ばそうとする教育は、定型発達の人にとっても望ましいものであり、ASDを含む発達障害の人にとって生きやすい社会は、定型発達の人にとっても生きやすい社会である。