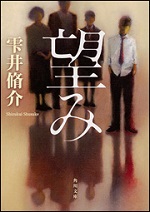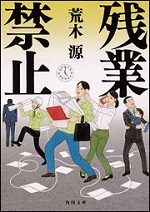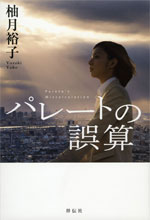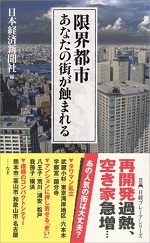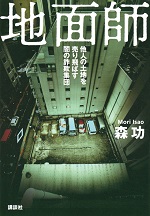Author Archives: kogakusha
清水ひろしからの手紙 84
『望み』 雫井脩介
『残業禁止』荒木源
『「自己肯定感」を高める子育て』 ダニエル J シーゲル / ティナ ペイン ブライソン 著, 桐谷 知未 訳

- 出版社:大和書房
自己肯定感を高めるには、「キレない力」「立ち直る力」「自分の心を見る力」「共感する力」の4つの資質が必要だ、と著者は記しています。
著書では、人間の感情を3つの状態に分けて説明しています。
人間の感情は、バランスのとれている状態では「グリーン・ゾーン」にあるが、恐れや動揺、怒り、いら立ち、恥ずかしさなどを感じると、急性のストレス反応を起こし抑えがきかなくなっている「レッド・ゾーン」、あるいは心を閉ざして内向きなってしまう「ブルー・ゾーン」に入ってしまう。
そのうえで、大人が子どもにすることは、キレてしまった時に「グリーン・ゾーン」に戻してやること、成長とともに「グリーン・ゾーン」を広げる手助けをすることだ、と述べています。

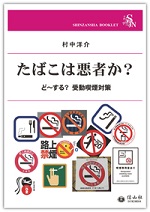
 清水ひろしからの手紙 84(PDFファイル)
清水ひろしからの手紙 84(PDFファイル)