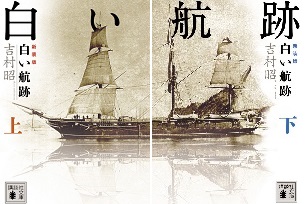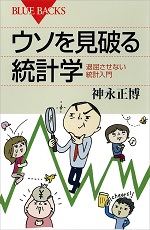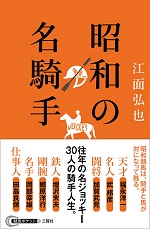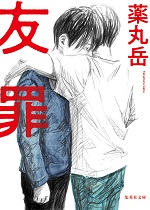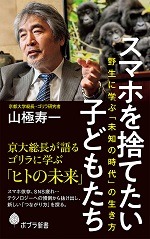『「さみしさ」の力 ─孤独と自立の心理学』 榎本 博明

- 出版社:ちくまプリマー新書
現代は、自立のために必要な「さみしさ」の足りない時代ではないか。今の人たちは誰かとつながっていないと不安。が、つながっていても物足りない。結局ますます一人でいられずSNSが逃げ場となる。しかし、SNSでのメッセージや情報に反応する受け身の過ごし方では自分を見失う、と著者は現状を認識し指摘しています。
そのうえで、「さみしさ」を感じて一人になって自分と向き合い、自分の中に沈潜しなければ心の声は聞こえてこない、一人の時間だからこそ思考も深まり、見えてくるものがある、と述べています。
刺激を絶ちあえて退屈な状況を生みだすことや、一人で行動できるというのはかっこいいことなのだ、という意識改革が必要だとも記しています。