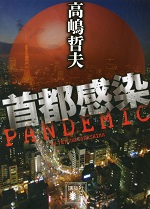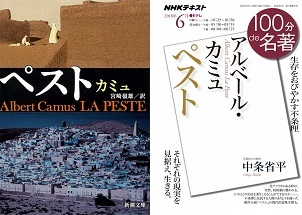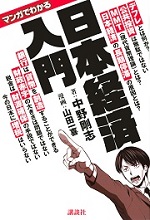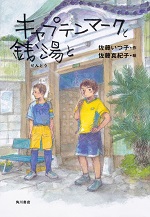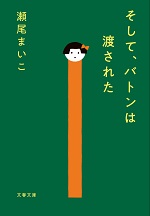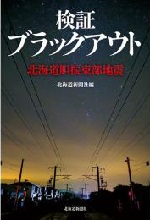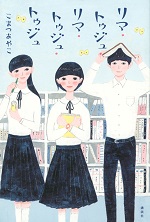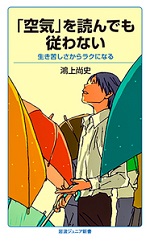『女子校礼讃』辛酸なめ子
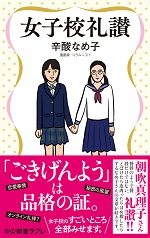
- 出版社:中公新書ラクレ
著者は女子校(女子学院)出身者。
学校や生徒への取材等による女子校の慣習や生徒の実情が、学生の時の思い出とともに、率直な感想とユニークな視点で記されています。御三家や大学付属など含め20校以上が登場し、文化祭や学校説明会だけでは分からない各校のカラーも知ることができます。
私も男子校で楽しい中高6年間を過ごしました。今でも良かったと思っています。
著者が自身のエピソードとして早弁をあげています。「今思えば、あえて授業中に食べる必要性はどこにもなかったです。ただスリルを楽しみたかったのだと思います・・・。」
・・・分かる気がします。
別学、共学それぞれ良さがありますが、著者が述べている「あの6年間が生命力の源泉になっているように思います。」は、男子校で育った私も同じ思いです。