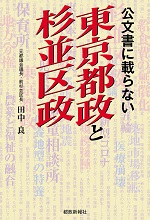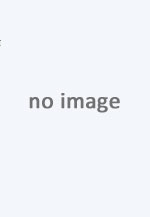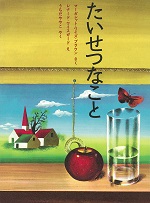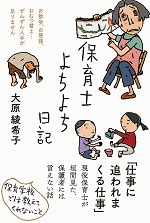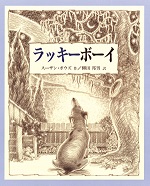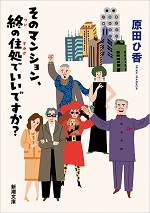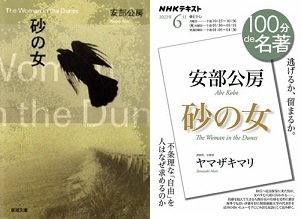『100分de名著 ル・ボン 群集心理』 武田砂鉄 著
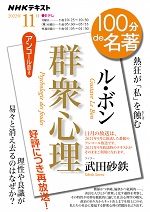
- 出版社:NHKテキスト
ル・ボンは、(1)感情や観念が同一の方向に向かう (2)意識的な個性が消えうせる という特定の心理作用を起こした人々の集団を「群衆」と呼んでいます。
その「群衆」は、分かりやすくインパクトの強いドグマ、心象によって物事を考えるため、為政者は断言と反覆と感染によって考える力を奪っていきます。
群衆にならないためには、(1)経験や知恵を堅持し、それをつねに頭に置いておくこと (2)自分で考えることを愚直に貫くこと (3)物事を鵜呑みにしないこと、疑う視点を持ち続けること、人と違う意見をもつことを怖がらないこと (4)「自分」という主体を強く意識し、「自動人形」になっていないか自問すること (5)安易に「わかったつもり」にならないよう、自分の知らないことに自覚的であること が重要だとしています。