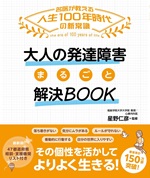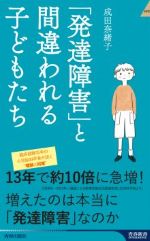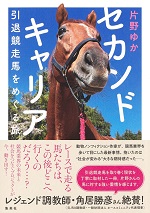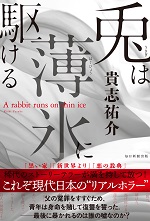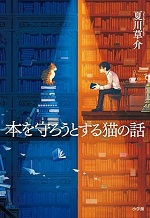私の本棚
清水ひろしが最近読んだ本をご紹介いたします。
『「発達障害」と間違われる子どもたち』 成田 奈緒子 著
『ルポ 高学歴発達障害』 姫野桂 著
『発達障害「グレーゾーン」』 岡田尊司 著
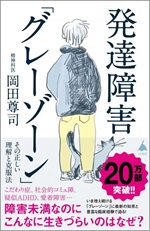
- 出版社:SB新書
以下のように記されています
・グレーゾーンは特有の生きづらさがあり、それは障害レベルの状態とは質的に異なる困難さだとも言える。グレーゾーンのケースには愛着や心の傷といった問題が絡んでいることが少なくない。グレーゾーンは単なる「障害未満」の状態ではなく、性質の異なる困難を抱えていることも多く、本人が味わっている苦労や大変さは、決して本来の発達障害に勝るとも劣らない。
・グレーゾーンと診断された場合、むしろ、これからの働きかけや取り組みによって大きな違いが生まれるため、しっかりサポートしていく必要がある。できるだけ早くから療育やトレーニングを行うことが、予後を改善することにつながる。
・大事なのは、障害か障害でないかを区別することでなはく、ベースにある特性をきちんと把握し、その人の強みと弱い点をきちんと理解し、適切なサポートやトレーニングにつなげていくこと。グレーゾーンと判定されるレベルでは、とくにそのことが重要になる。
・近年、発達の特性は、障害ではなくそれぞれの人がもつ脳の特性であり、ニューロダイバーシティ(神経多様性)として理解されるようになってきている。
『その「一言」が子どもの脳をダメにする』 成田奈緒子・上岡勇二 著
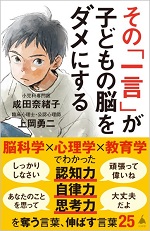
- 出版社:SB新書
脳は繰り返し入ってくる刺激を重要なものだと判断してしまうため、親から子どもへ否定的な言葉がけはネガティブな脳を育ててしまう、と指摘しています。
そのうえで、親は生きていく上で本当に必要な家庭生活での「軸」2~3本のみを持って子育てをしていくことが、脳育てにおいて一番大切なことだ、と訴えています。
そして、生まれたときに「心配100/信頼0」だった子どもを、18歳で「心配0/信頼100」で送り出すために、言葉は「ロジカルに」「フルセンテンスで」伝え、「知恵者」として「一枚上手」に、子どもの能力をどんどん伸ばしてあげましょう、と述べています。
子どもの脳を育てる言葉がけ5か条
1) 「子どもの脳を育てる」ことを念頭に置く
2) 大人は子どもより「一枚上手」の「知恵者」になる
3) 子どもが不安になっているときには「オウム返し」
4) 中学生以上の子どもには「年上の友人」のつもりで接する
5) 子どもに話せる自分自身の経験(フィクションでもよい)をストックする
『セカンドキャリア 引退競走馬をめぐる旅』 片野ゆか 著
『兎は薄氷に駆ける』 貴志祐介 著
『詭弁社会』 山崎雅弘 著
『日本人という呪縛』 デニス・ウェストフィールド 著

- 出版社:徳間書店
著者は在日オーストラリア人のジャーナリスト。
多様性を認めない日本の社会や集団、世界標準からかけ離れた日本のメディア、自国民を守れない外交、景気低迷を政府の経済失策と見ず、政治の変革を拒んできた国民・・・。
予定調和と現状維持を崩さないように「政治」と「官僚」と「メディア」が変革を頑なに阻んでいる。その結果、国民は社会が受け入れる基準に沿って考えさせられているということに、日本人はまず気付いて欲しいと訴えています。
日本人は意識せずに自分で自分に呪縛を与えていると指摘し、今までの「常識」を疑い、日本人的価値観に縛られていることを見つめ直し、制度やシステムから自由と人間性を取り戻すべきだ、とオーストラリアの例なども示しながら記しています。